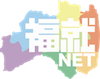こんにちは、福島就業支援ネットワーク事務局です。
今回の研修報告は先日1/18~1/19行われた「共感∞つなぐvol.4」の2日目の講演会についての記事です。
今回の研修テーマ「共感∞つなぐ~未来に向かって~」ですが、研修を受講した人がそれぞれ何かに”共感”し事業所に持ち帰って繋いでいく
研修で刺激を受けてモチベーションにし、支援で悩む場面があるとしたら、新たな発想の転換のきっかけになれば良い。
そんな思惑があって企画されてきました。
講師陣を決めていく際もどんな話が聞きたいか?など意見交換がされてきましたね。
それから”いわき市開催”ということもあり、いわき市の取り組みの中からも考えていった結果、
「いわきの地域包括ケア igoku(いごく)」という取り組みについてお願いをする事になりました。
高齢者分野の取り組みではあるが、地域包括ケアという仕組みから障害分野でも学べる事がたくさんあるのではないかと思ったからです。
さて、話を研修2日目の当日に戻して、

2日目もたくさんの方にお集まりいただけました。80名くらいはいたでしょうか。
この日は前日の分科会の報告発表から始まり、いよいよ基調講演です。
最初に登壇されたのは、いわき市保健福祉部地域包括ケア推進課の猪狩僚さん。
バリバリの行政マンです。

え?バリバリの行政マン…?
行政マンのイメージが違う…と印象持たれた方が多いのではないでしょうか?
帽子を被ってパーカー姿。
私のイメージしている行政マンとは違う。。
猪狩僚さんは”地域包括ケア推進課”といういわき市役所で新しい課(H28.4~)ができた時に配属されたそうです。
それまでは、水道局、公園緑地課、財政課、行政経営課などを渡り歩いてきた為、高齢者・福祉の分野は初めてで、全く現場を知らない状態からのスタートだったそうです。
なので最初の一年は”知る”為に色々な職種の勉強会や集まりに参加する活動がメインだったと話をされていました。
そこで、”福祉の現場にはこんな熱い支援者がたくさんいる、これって関わっていないと誰も知らないんじゃないか?”と感じ、当事者やその家族、支援者やそれぞれの取り組みを”見える化”していこうと始まったのがメディアの「igoku」だったんですね。(https://igoku.jp/)
取り組み自体がとてもユニーク。
タブーとされている「死」をテーマにした「igoku Fes!」を開催したり、いわきで活躍されている高齢者の方にインタビューしてメディアで取り上げたり、フリーペーパーを発行したり様々な形で知る機会を作っています。
地域包括ケア推進課が掲げる”私たち(いわき)が目指す姿
「誰もが、住み慣れた地域や自らが望む場で(どんな状態になっても)暮らし続けることができるまちづくり・地域づくり」
これって高齢者だけではないですよね、障害とか年齢とか関係なく共通している所だなと感じました。
病院ではなく、地域で支える”地域包括ケア”がどうして普及していかないか?猪狩さんはこう言いたました。
要因1:そもそも、在宅で医療や介護が受けられることを、“知らない”
要因2:どこで最期を迎えたいかということを、本人・家族が“考えない”
要因3:本人の意向を尊重したいと思いつつ、家族的には“こわい・不安”
猪狩さんは3つの要因を述べ、「igoku」のターゲットを高齢の方にとどめず、いわき市民全員、特にこれから親を看取る40代~50代としたと話されました。
そして、igokuを運営しているメンバーは市役所の職員ではなく、いわき市に在住しているクリエイターのチームで共創しており、メンバーは映像、デザイン、グラフィック、ライターなどまさに仕事内容がクリエイティブでした。
猪狩さんは、一度はいわきを離れ都会で仕事をしていた人が、いわき市の取り組みを発信し、作っているいわき市民を見える化することで、いわきにこんな人がいるんだ、自分も地元で働きたい、地元に戻りたいという化学反応を期待しているとか。
いや~、そこまで考えていたとは驚きました。
まさに「誰もが住みやすいまちづくり」をするには、福祉側だけで取り組むのではなく、市民が(誰もが)地域課題を知り取り組み仕掛けづくりが必要だと実感しました。

福島就業支援ネットワークという障がいある方の就労を支援するネットワーク団体が高齢者の地域包括というテーマでセミナーをやることは、初の試みだったのではないでしょうか。
今回は他分野から学ぶことが本当に大きかったと実感しています。
これからも「igoku」の動向は見逃せない!